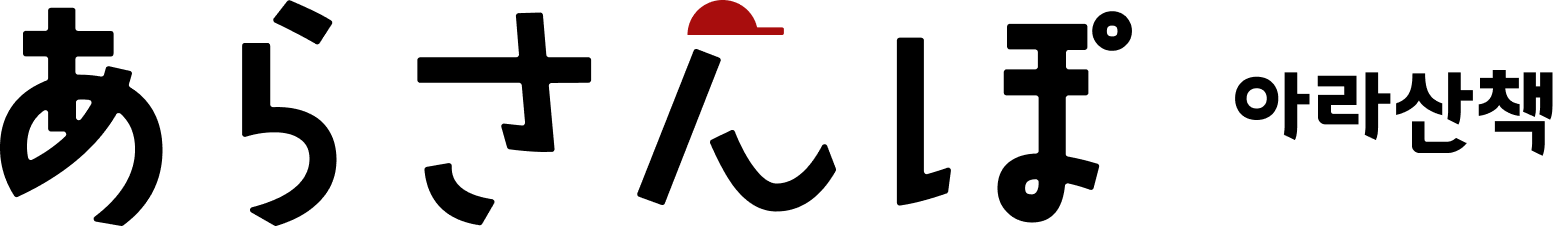荒川区に住んで3年になりますが、つい先日、西日暮里をぶらぶら歩いていたときに偶然発見したのが「太平洋美術会」でした。諏方神社のちょうど向かい側にあるこの建物、実は日本最古の洋画美術団体だということを知って驚きました。中に入ってお話を伺うと、この場所と団体の歴史について詳しく教えてくださり、すっかり魅了されてしまいました。
明治22年創立!日本洋画界の源流がここに
太平洋美術会は、明治22年(1889年)に「明治美術会」として創設されて以来、明治、大正、昭和、平成、令和の五世代にわたる輝かしい伝統を築き上げてきた、我が国の洋画及び彫刻界における最古の歴史を誇る団体です。
明治35年(1902年)、ヨーロッパから帰国した新進作家、吉田博、満谷国四郎、中川八郎、丸山晩霞らを中心として、明治美術会の後身として「太平洋画会」が結成されました。その後1957年に「太平洋美術会」と改称し、現在に至っています。
私がお話を伺った際に印象的だったのは、長い歴史の中で多くの優秀な美術家を育ててきたという教育機関としての役割でした。在野の立場から美術教育を続けてきた伝統には、本当に感動しました。
豊島区から移築された日名子実三のアトリエが校舎に
現在の建物には本当に興味深い歴史があります。実は、この建物は約100年前から豊島区にあった彫刻家・日名子実三のアトリエを、そのまま西日暮里に移築したものだそうです。
太平洋美術会の校舎はもともと谷中にありましたが、昭和20年3月の戦災で焼失してしまいました。新たな拠点を求めて荒川区のこの地に移転することになった際、移築されてきた日名子実三のアトリエが校舎として生まれ変わったのです。
余談ですが、日名子実三の師匠は、あの有名な朝倉文夫なんです。日名子実三といえば、日本サッカー協会のヤタガラス(八咫烏)のシンボルをデザインしたことで知られる彫刻家です。その師匠である朝倉文夫の台東区立朝倉彫塑館も近所にあるので、この一帯は師弟関係でつながった彫刻家たちの足跡を感じることができる、まさに芸術の聖地といえるでしょう。

実際に建物に入ると、ジブリ映画に出てきそうな自然光の優しく差すアトリエの雰囲気が残っていて、こんな贅沢な環境で美術を学べるなんて本当に素晴らしいと感じました。


太平洋美術会研究所とギャラリー太平洋
現在、太平洋美術会は研究所とギャラリーの2つの機能を持っています。
太平洋美術会研究所
めざすジャンルは絵画?彫刻?版画?造形の専門家をめざす方はもとより、生きがいづくりの生涯学習として実技を学びたいという方も、経験と実績を積んだ現役作家の講師陣が懇切に対応。基礎から専門技術まで一人ひとりの個性に合せて、最適の個人指導を行っています。
教室が充実しているということで、継続的に美術を学びたい方には理想的な環境です。洋画、彫刻、版画、染織の各部があり、初心者から本格的に取り組みたい方まで幅広いニーズに対応しているようです。
ギャラリー太平洋
ギャラリー「太平洋」は、当会の作家のみならず、地元の荒川区民の皆様など、広く一般にも開放しています。これは地元住民としてとても嬉しい情報ですね。プロの作家だけでなく、私たち地域の人々も展示の機会を得られるというのは素晴らしいことです。
毎年開催される太平洋展の迫力
太平洋美術会の大きなイベントとして、毎年5月に国立新美術館で開催される太平洋展があります。2025年5月14日から26日まで、第120回記念太平洋展が開催され、その歴史の重みを感じる展示が行われました。
「荒川区に日本で一番歴史がある美術団体があるのは誇らしい気持ちになります」という地元の方の声にも、私は深く共感しています。西日暮里という身近な場所に、これほど歴史と格式のある美術団体があることを知ると、この街への愛着がさらに深まります。
アクセスと周辺環境
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式名称 | 一般社団法人 太平洋美術会 |
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里(諏方神社向かい) |
| 最寄駅 | JR山手線・千代田線「西日暮里駅」徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-3821-4100 |
| FAX | 03-3821-7319 |
| 設備 | 太平洋美術会研究所、ギャラリー太平洋 |
| 対応分野 | 洋画、彫刻、版画、染織 |
立地的にも非常に便利で、西日暮里駅から歩いてすぐの場所にあります。第一日暮里小学校の門から、富士見坂方向歩いていくと、諏方神社があります。そのちょうど向かい側に位置するため、地域散策の際にも立ち寄りやすい場所です。